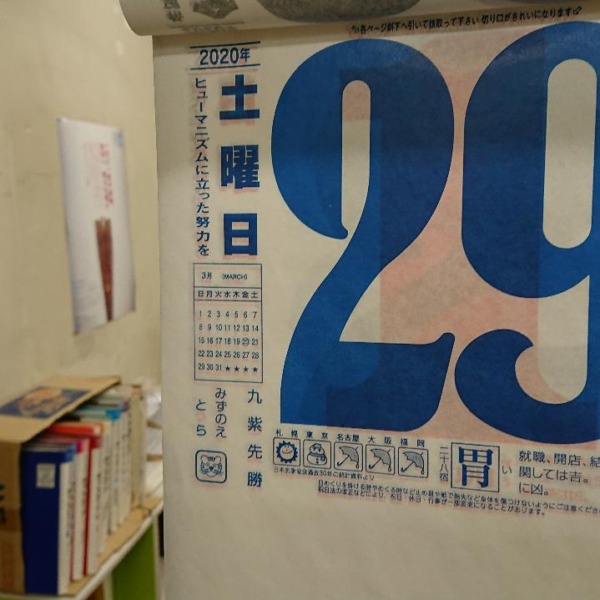読めますか? テーマは〈書く〉です。
目次
敲く
たたく
(正解率 81%)「叩く」とほぼ同じ意味。ともに常用漢字ではないので、新聞では「たたく」と仮名書きにする。しかし音読みは熟語「推敲(すいこう)」でよく使われ、オバマ米大統領の広島演説の原稿も自分で推敲したという記事が出た。唐の詩人が自分の作る詩で、門を「推(お)す」か「敲く」か迷ったことに由来する言葉だ。
(2016年06月13日)
選択肢と回答割合
| とどく | 9% |
| つらぬく | 10% |
| たたく | 81% |
認める
したためる
(正解率 70%)丁寧に手紙などを書くこと。昔は「整理・処理する」「食事をする」などさまざまな意味があったが、現代ではほぼ書くことに限定されている。ただし常用漢字表の訓読みは意味も異なる「みとめる」のみだ。
(2016年06月14日)
選択肢と回答割合
| まとめる | 8% |
| したためる | 70% |
| あらためる | 22% |
花押
かおう
(正解率 82%)自筆であることを証明するために書く、図案化された書体の記号。戦国・江戸時代の武将などが用いた。花押を記した遺言状が有効かどうか争われた訴訟で、最高裁判所は「花押は印章による押印と同視できず無効」と判断した。
(2016年06月15日)
選択肢と回答割合
| かおう | 82% |
| かこう | 9% |
| はなおし | 9% |
遺言証書
いごんしょうしょ
(正解率 36%)法定の方式で遺言を記載した書面。一般的に「ゆいごん」と読む遺言は法律用語では「いごん」。また、故人ののこした言葉の意味では「いげん」の読みもある。
(2016年06月16日)
選択肢と回答割合
| ゆいごんしょうしょ | 58% |
| いげんしょうしょ | 7% |
| いごんしょうしょ | 36% |
擱く
おく
(正解率 25%)やめること。書くことをやめる意味の「筆を擱く」という形で主に使われるが、常用漢字ではない。「筆を置く」だと机の上などに置く物理的な動きのように誤解されかねないので、新聞ではやめる意味では「おく」と仮名書きにしている。
(2016年06月17日)
選択肢と回答割合
| はじく | 36% |
| おく | 25% |
| かく | 39% |
◇結果とテーマの解説
(2016年06月26日)

この週は「書く」をテーマにしました。きっかけは、花押を記した遺言状が有効と認められなかったというニュースと、オバマ米大統領が広島演説の原稿を自分で推敲していたという報道です。
「敲く」の出題時「『叩く』とほぼ同じ意味」と書きましたが、「ほぼ」は全く同じとは限りません。どういう違いがあるのでしょう。「漢字の使い分けときあかし辞典」(円満字二郎著、研究社)によると
この漢字の右半分の「ぼくづくり」は“棒や鞭などで打つ”ことを表す部首。つまり、《敲》は“手や棒などで打つ”ことをかなり明確に表す。
そこで、勢いよく「たたく」とか、「たたく」音が響き渡るといった雰囲気を表現したい場合に用いるのが、ふさわしい。
ただし「叩」「敲」とも常用漢字ではないので新聞では仮名書きになります。
「したためる」も仮名書きです。「認める」だと、どうしたって「みとめる」と読んでしまいますからね。「したためる」は「書く」のほかにも「食事をする」「しかるべく処置する」「用意する」「治める」などの意味があるそうです。「暮らしのことば語源辞典」(講談社)によると、「『したた』は、心がこもっていて確かであることで、『したたか』などと同源」とのことです。
「花押」は今回最も正解率が高くなりましたが、常用漢字である割に、そう高い数字とはいえません。自分で使う人は現代では政治家くらいかと思っていましたが、一般の人でも実際に使う人がまだいたんだと思わされたのが、今回の遺書に関する裁判でした。
「遺言証書」は法律用語。新聞では「遺」の読みとして「イ」「ユイ」ともに認められていますので、通常ルビはつけません。だから読みが問題になることはないのですが、法律的には一般と違う読み方をするものが他にも少なくありません。例えば「立木」は法律用語では「りゅうぼく」と読みます。一般語として「たちき」と読むなら新聞では送り仮名が必要になります。どこまで法律用語に忠実にすべきかという判断は別として、一般語と誤解して校閲で反射的に送り仮名を付すのは避けたいもの。そういえば毎日新聞では一般的には「6カ月」と書くのに、判決では「ろくげつ」という読み上げに合わせてか「懲役2年6月」などと表記しています。個人的には妙な慣行だと思いますが……。
「擱く」は今回正解率最低。これも常用漢字ではないので新聞では「おく」と仮名書きにします。だったらなぜこんな字を問題に出すのかというと、「筆を置く」という表記に注意してほしいという思いからです。「擱筆(かくひつ)」という、筆をおいて書くのをやめることを表す熟語があるので、その意味では「筆を置く」ではなく「筆を擱く」が適切なのです。では、この稿の筆をおきます――とまとめようと思いましたが、パソコンなのでやめておきます。