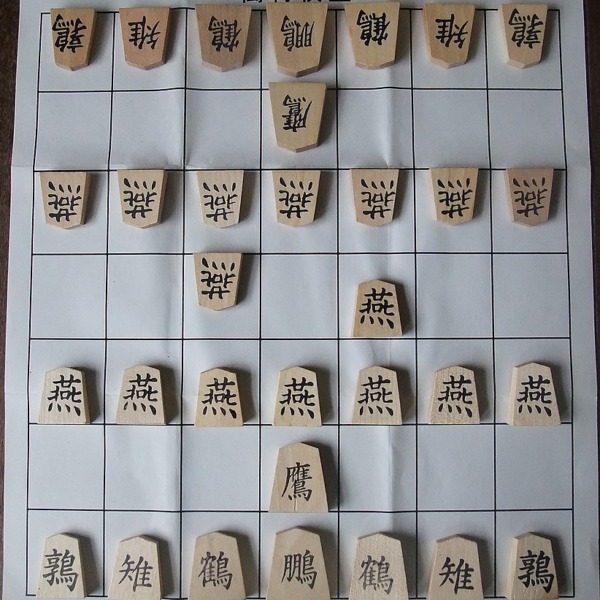読めますか? テーマは〈暖房〉です。
目次
頭寒足熱
ずかんそくねつ
(正解率 70%)頭は冷やし、足は温めること。今年没後100年となる夏目漱石の「吾輩は猫である」に「頭寒足熱は延命息災の徴」とあるように、昔から健康によいとされる。
(2016年01月18日)
選択肢と回答割合
| ずかんそくねつ | 70% |
| あたまさむあしあつ | 0% |
| とうかんそくねつ | 29% |
炭団
たどん
(正解率 83%)「たんどん」ともいう。木炭や石炭の粉末を球状に固めた燃料。それが転じて、相撲の黒星のことも表すようになったが、今は炭団そのものが使われないのであまり一般的ではない。なお東京都文京区には炭団坂がある。
(2016年01月19日)
選択肢と回答割合
| たんだん | 11% |
| すみまる | 6% |
| たどん | 83% |
温石
おんじゃく
(正解率 68%)焼いた石を布に包み体を温めるのに使ったもの。懐炉の元になったとされる。一方、懐石料理の石とは本来、禅宗の修行僧が空腹を紛らすために懐に入れたもの。千利休が懐石料理の質素な原形を作ったという。
(2016年01月20日)
選択肢と回答割合
| おんせき | 24% |
| おんじゃく | 68% |
| あついし | 8% |
熾す
おこす
(正解率 60%)炭火などの勢いを盛んにすること。または火をつけること。「火を起こす」という表記は必ずしも間違いとは言えないが、「熾す」の方が適切。ただし常用漢字ではないので新聞では平仮名にしている。
(2016年01月21日)
選択肢と回答割合
| もす | 6% |
| おこす | 60% |
| ともす | 34% |
埋火
うずみび
(正解率 44%)長持ちさせるために灰に埋めた炭火。手をかざすとほのかにぬくもりが。「埋火や春に減りゆく夜やいくつ」「埋火やありとは見えて母の側(そば)」(与謝蕪村)。今年は蕪村生誕300年だ。
(2016年01月22日)
選択肢と回答割合
| うもれび | 51% |
| うずみび | 44% |
| まいか | 5% |
◇結果とテーマの解説
(2016年01月31日)

この週は「暖房」。
「頭寒足熱」は割によく見る言葉と思っていましたが、3割近くが誤答。目で字を見てはいても耳には残っていない人が多いのでしょうか。なお夏目漱石の「吾輩は猫である」に「頭寒足熱は延命息災の徴と傷寒論にも出て居る」とありますが、傷寒論というのは西暦250年ごろ成立した中国の医書で、漢方医学の聖典とされているそうです。日本の「こたつ」は頭寒足熱の理にかなっていますね。
「炭団」は逆に、今は全くといっていいほど見かけないにもかかわらず、今回最も正解率が高くなりました。選択肢が簡単すぎたのか、使わなくても知識として知っている人が多いのか分かりかねます。大友克洋「AKIRA」にこの字のマシンが出るようですが、有名な漫画とはいえそれで分かった人がたくさんいたとはちょっと思えません。
「温石」の出題時の解説で懐石料理の語源に触れました。杉本つとむ「語源海」(東京書籍)によると、
〈懐石料理〉は茶の湯で茶をすすめる前にだす軽い馳走をさす(のち、入浴する)。懐石は〈禅林にて菜石と云に同じ、温石を懐にして懐中をあゝたむる迄の事なり〉(喫茶南方録=南坊録。千利休口述)
懐石料理はそうしたごく粗末な、いわば精進料理の類であった。
しかし〈会席料理〉はその伝統を学んでいるものの、むしろ逆に豪華に変じている。
とあります。今はその「懐石料理」も粗末なイメージがなくなり「会席料理」との区別が難しくなっているのではないでしょうか。
「熾す」の字は訓よりも漢語の「熾烈」で使われることが多いのではないでしょうか。しかしいずれにせよ常用漢字ではないので、新聞では「火を熾す」は「火をおこす」にし、「熾烈」は「激烈」「激しい」などへの書き換えを校閲としては勧めています。
「埋火」は今回最も正解率が低くなりました。引用した蕪村の句
埋火やありとは見えて母の側(そば)
は歳時記によっては初めが「埋火の」となっていますが、角川ソフィア文庫「蕪村句集」などの表記に従いました。出題者は初めてこの句に接したとき「埋火があるように感じられたが、母親のそばのぬくもりだった」という意味で、埋火は実際にはなかったものと解釈していました。しかし角川文庫の玉城司さんの訳では「埋火がたしかにあると感じられる温もり、まるで亡き母の側にいるよう」となっています。解説によると「埋火の温もりから亡き母を思い出して追慕した」とあり、母親が亡くなった後のことだということです。すると埋火は存在するということになりそうです。
ただ、句の解釈は人それぞれでいいとすると、母親が生きているころのことを回想して詠んだのだと思っても、大きな間違いではないのではないでしょうか。いずれにしても、母親のぬくもりをしみじみと感じさせる名句だと思います。