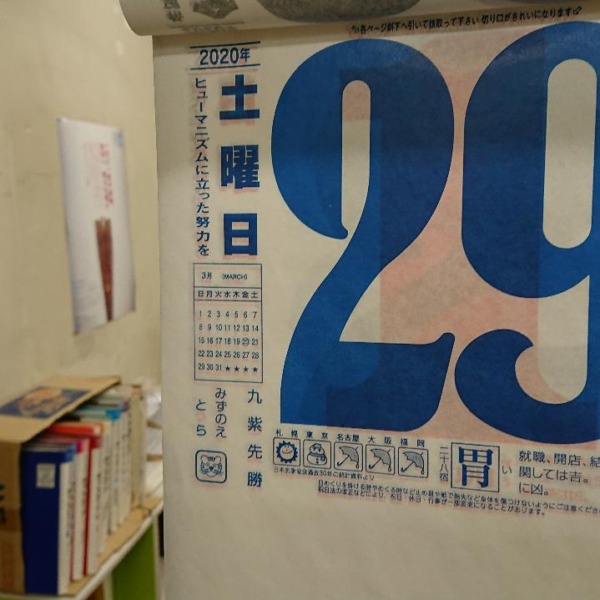読めますか? テーマは〈八幡〉です。

石清水八幡宮
目次
八幡市駅
やわたしえき
(正解率 63%)
京都府八幡市にある京阪電鉄の駅。今秋に国宝指定の答申があった石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)の最寄り駅だ。
(2015年12月21日)
選択肢と回答割合
| やわたしえき | 63% |
| やはたしえき | 27% |
| はちまんいちえき | 10% |
穴八幡宮
あなはちまんぐう
(正解率 86%)
東京都新宿区西早稲田の神社。冬至の日から、陰が極まり陽が復活することにちなんだ「一陽来復」のお守りを扱うことで知られる。
(2015年12月22日)
選択肢と回答割合
| あなはちまんぐう | 86% |
| あなやはたぐう | 5% |
| あなやわたぐう | 9% |
八幡東区
やはたひがしく
(正解率 56%)
北九州市。今年、世界文化遺産に登録された官営八幡製鉄所関連施設がある。現在の八幡製鉄所の読みは「やはた」だが英語表記はYawata。またJR九州駅名も八幡(やはた)駅だ。
(2015年12月24日)
選択肢と回答割合
| やはたひがしく | 56% |
| やわたひがしく | 39% |
| はちまんひがしく | 4% |
群馬八幡駅
ぐんまやわたえき
(正解率 39%)
群馬県高崎市のJR信越線駅。1月6、7日に開かれる「高崎だるま市」が有名な達磨寺の最寄り駅。なお、全国的に八幡の付く駅は多い。読みはほとんど「はちまん」か「やわた」だ。
(2015年12月25日)
選択肢と回答割合
| ぐんまはちまんえき | 40% |
| ぐんまやわたえき | 39% |
| ぐんまやはたえき | 21% |
◇結果とテーマの解説
(2016年01月03日)
「群馬八幡駅」の解説で記したように、駅名では「やはた」はほとんど見られないということはありますが、それ以外でも「やわた」と「はちまん」が同じくらい散らばっていますので、一つ一つ覚えなければなりません。群馬八幡駅は、高崎のだるま市(6、7日)で有名な寺の最寄り駅ということで選びましたが、正解率はこの週で最も低くなりました。
「八幡市駅」は初詣の人気スポット「石清水八幡宮」が近くにあり、既にこれだけで「やわた」「はちまん」の読みが混在しています。ところで出題時、解説に「石清水八幡宮の最寄り駅」と書いていました。京阪本線の最寄り駅としては間違いないのですが、同駅から出ているケーブルカーの「男山山上駅」が石清水八幡宮のすぐそばですので、厳密にはよくありませんでした。今は「近く」と直しています。
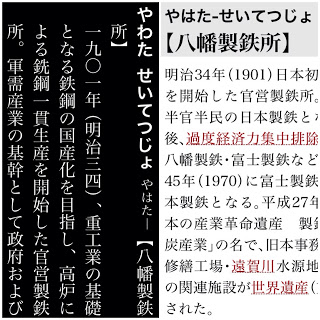
左は大辞林3版、右は大辞泉。共にiOSアプリ版より
ちなみに、柳田国男は八幡神について鍛冶の技術を持つ士族集団の氏神だったという仮説を唱えているとのこと。「日本の神々と仏」(青春出版社)によると、
かれらは移り住んだ先々で一族の氏神を祭ったと考えられ、八幡が全国に広がった理由が、これで理解できる。
日本有数の製鉄の町が福岡県北九州市、かつての八幡市にあったのも偶然ではないだろう。
とすると、「はた」は古代日本に渡来した秦氏からきたのでしょうか。それが一方で「は」から「わ」への転、一方では「はちまん」へと転じていったのでしょうか。しかし「八」は何のこと? 知的好奇心は尽きません。