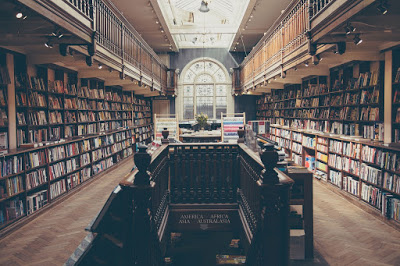読めますか? テーマは〈別字体〉です。
目次
圀
くに
(正解率 81%)「国」と実質的に同じ字なので「コク」とも読める。中国・唐の則天武后(そくてんぶこう)が制定した則天文字の一つ。日本人名として最も有名なのは徳川光圀(みつくに)。黄門様だ。
(2015年06月29日)
選択肢と回答割合
| えん | 11% |
| くに | 81% |
| その | 8% |
埜
の
(正解率 67%)「野」と読みも意味も同じ字なので「ヤ」とも読めるが、人名、地名では「の」が普通。Jリーグ・ベガルタ仙台の奥埜博亮選手や、合併前の千葉県本埜(もとの)村など。
(2015年06月30日)
選択肢と回答割合
| そ | 27% |
| の | 67% |
| はやし | 6% |
閠
うるう
(正解率 74%)暦で平年よりも月や日などが多いこと。閏(音読みでジュン)は人名用漢字。だが問題として掲げた字は「もんがまえ」の中が「玉」。中が「王」の「閏」と意味も読みも同じ字だが、「閠」という字の名前は認められない。2015年7月1日午前9時直前にうるう秒が実施された。
(2015年07月01日)
選択肢と回答割合
| うるう | 74% |
| かん | 11% |
| ぎょく | 16% |
晉
しん
(正解率 78%)「晋」の旧字体。安倍晋三さんが批判を浴びてムムッとしている字ではない。晋は人名で「すすむ」とも読む。中国古代の王朝名としても有名。
(2015年07月02日)
選択肢と回答割合
| しん | 78% |
| ふ | 12% |
| ろ | 11% |
邨
むら
(正解率 50%)「ソン」とも読む。「村」と意味も読みも同じ字。「中邨(なかむら)」などの姓や、俳人・山口青邨(せいそん)、加藤楸邨(しゅうそん)の号で知られる。
(2015年07月03日)
選択肢と回答割合
| きゅう | 7% |
| とん | 43% |
| むら | 50% |
◇結果とテーマの解説
(2015年07月12日)
この週は人名などに使われる「別字体」を並べました。「異体字」ともいいますが、この言葉は一般的にはあまり知られていないようです。また「晋」の旧字体を出し、旧字も異体字の一種ではありますが、職場では旧字と異体字を使い分けていることも「異体字」をテーマ名にしなかった理由の一つです。
別字体といっても「別字」とは違います。たとえば「王」と「玉」は点がつくかつかないかだけの違いですが異なる文字、つまり別字です。しかし「閏」と「閠」は同様に点の有無ですが、同じ字で字体が違うだけの別字体です。
毎日新聞では原則として、旧字・異体字は使わず、たとえば「栁」は「柳」に、「曾」は「曽」に直しています。しかし旧字・異体字には私たちが通常使う字ととんでもなく形が違うものもあります。今回の例では「埜」と「野」、「邨」と「村」が同じ字だなんて、教えられないと想像もつきません。不用意に「中邨」を「中村」に直してしまうと「間違いだ」としかられるでしょう。だからこのような字は使用実態に即してそのままにせざるをえません。
ここで番外編の問題ですが
〇
という、マルみたいな、というかマルそのものの字があります。何の別字体か分かります? 漢字ですが普通の漢和辞典に載っていません。実際に使われていたかどうか分かりませんし、ほぼ使われなかったから漢和辞典に載っていないのでしょう。
これは中国・唐代の則天武后が制定した「則天文字」の一つ。「星」と同じだそうです。これに限らず則天文字はほとんど普及しませんでした。しかし現代日本でも堂々と使われている則天文字があります。
 |
| by Kentaro Ohno |
それが「圀」。このたび「水戸黄門」がスペシャルドラマとして復活、冲方丁さんの「光圀伝」も文庫になったので、この字の出題チャンスと思いました。
杉本つとむ著「漢字百珍―日本の異体字入門」(八坂書房)にこうあります。
言い伝えによれば、〈國〉の字のように、〈囗〉の中に〈惑〉を連想させたり、〈武〉の意がこめられている〈或〉があるのはよろしくないという発想から、単純明快に〈囗〉と〈八方〉の組みあわせをもってクニの字としたそうです。(中略)光圀は別に、武后にあやかろうとして〈圀〉の字を選択したわけではないでしょう。〈圀〉の字は、創作して間もなく日本にも伝えられ(中略)鎌倉時代に成立したと思われる字書、『類聚名義抄(るいじゅうみょうぎしょう)』などにもこの〈圀〉はみえるのです。
ここで番外編の問題その2。「漢字百珍」に載っていたのですが、
囻
は何の異体字でしょう。
実は「圀」と同じく「国」の異体字。奈良時代の書物「令義解(りょうのぎげ)」の中に用いられているそうです。「國」の略字としてはかつて中が「玉」ではなく「王」が使われていたようですが、城壁を表す「くにがまえ」の中を「王」ではなく「民」に変化させるなんて、奈良時代の人もなかなか民主的ですね。民衆よりも国家を大事にする為政者にはぜひ知ってほしい字です。国の主役は民なのですから。