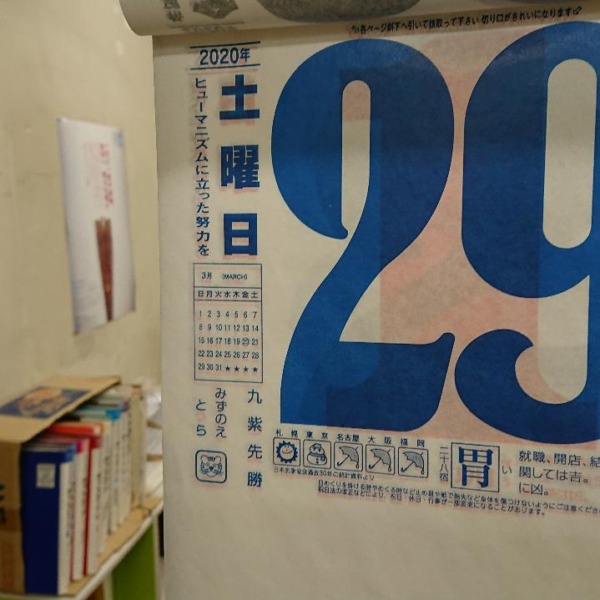読めますか? テーマは〈落語〉です。
紫檀楼古木
答え
したんろうふるき
(正解率 32%)登場人物の名前がそのまま演題になっているが、この人物は江戸後期に実在した狂歌師(後に「古喜」と改名)で、「らお屋」、つまりキセルのすげ替えを本業としていた。「紫檀」は木材の名。なお本日(6月第1月曜日)は「寄席の日」で、東京の寄席はほぼ半額で入場できる。
(2014年06月02日)
選択肢と回答割合
| したんろうふるき |
32% |
| しだんろうこぼく |
64% |
| むらさきだんろうふるぎ |
4% |
平林
答え
ひらばやし
(正解率 59%)平林さんへの手紙を届けるよう頼まれたが、読み方を忘れてしまい、宛名を見せ周りの人に尋ねるも「たいらばやし」「ひらりん」、漢字を分解した「いちはちじゅうのもくもく」などと、みんな違って大弱り――という話。江戸初期の笑話集「醒睡笑」がもとになっている。
(2014年06月03日)
選択肢と回答割合
| たいらばやし |
25% |
| ひらばやし |
59% |
| ひらりん |
16% |
武助馬
答え
ぶすけうま
(正解率 68%)役者になるという夢を諦めきれない、呉服問屋の奉公人・武助さん。ついに一念発起、芝居の一座に身を投ずることにした。それから数年、一座が江戸で芝居を打つことになり、かつての奉公先にあいさつに来た武助さんだが、彼の演じる役とは……。
(2014年06月04日)
選択肢と回答割合
| たけすけば |
12% |
| むっつりすけべ |
20% |
| ぶすけうま |
68% |
竈幽霊
答え
へっついゆうれい
(正解率 65%)竈は通常「かまど」と読むが、江戸落語の演題としては「へっつい」。売れてもすぐに返品されるへっついが幽霊を呼び寄せる。なお、足のない幽霊でなければオチにならないので、マクラで円山応挙が描いた足のない幽霊図に触れることも多い。
(2014年06月05日)
選択肢と回答割合
| かまゆうれい |
22% |
| すっぽんゆうれい |
13% |
| へっついゆうれい |
65% |
粗忽長屋
答え
そこつながや
(正解率 85%)粗忽は「軽率、そそっかしい」の意。粗忽者の出てくる落語は多いが、この話の2人の間抜けぶりは突き抜けている。「てめえは死んでる」と言われその気になった男は「じゃ、この俺は誰?」。聞きようによっては哲学的な話で、「中学生までに読んでおきたい哲学」(あすなろ書房)にも収録された。
(2014年06月06日)
選択肢と回答割合
| うかつながや |
4% |
| そこつながや |
85% |
| そそうながや |
11% |
◇結果とテーマの解説
(2014年06月15日)

今回、正解率が最も高かったのは、「粗忽長屋」でした。
実は6月1日の毎日新聞朝刊「ぶらっと落語歩き」(春風亭一之輔さんが古典落語の舞台を歩くという連載企画です)のテーマが「粗忽長屋」で、当然ながら紙面ではふりがなも付いていたのです。直前に載ったばかりというタイミングとなり、本紙の購読者の皆様にとっては造作もない問題だったでしょうが、おかげで紙面に出す問題をぎりぎりで差し替える羽目になりました。
次に正解率が高かったのは「武助馬」。回答するだけなら消去法で問題なかったはずですが、「武助」が登場人物の名前であることは、なかなか気づきにくいかもしれません。何といっても肝は「ヨッ、馬の脚! 後ろのほう! 武助馬、日本一!」という掛け声で、ばかばかしい半面、ほのぼのした話でもあります。
僅差で続いたのが「竈幽霊」です。もともと上方では「かまど幽霊」と呼ばれていたようですが、大正期に江戸落語に持ち込まれて以降、「へっつい幽霊」となっています。
「かまど」も「へっつい」もそれぞれ古い言葉ですが、例えば海外の文学作品の翻訳を読んでおりますと、「へっつい」はまずお目にかかりません。そうした言葉が、落語の中で特異点的に生き残っているというのは、なかなか興味深いものです。
意外に伸び悩んだのは「平林」でした。話の中で「タイラバヤシかヒラリンか」と歌い歩く場面が入りますので、確かに「ありそうな読み方」には違いないでしょう。ちなみに、元になったとされる「醒睡笑」ですと、「ヒョウリンかヘイリンか、タイラバヤシかヒラリンか……」などと続きます。
前座さんがかけることも多い話である半面、演ずるにはリズム感が不可欠なので、これを面白く聞かせる若手を見かけたら、名前を覚えておくと先の楽しみが増えるかもしれません。
さて、最も正解率が低かったのは「紫檀楼古木」でした。選択肢に「ふるき」と「こぼく」が並んでいれば、さすがに元から知っていないと厳しかったでしょうか。実在した人物が主人公となり、かつ演題にもなっている話は「西行」「中村仲蔵」など意外に多いですが、実力派がじっくり演ずる話が多い印象があります。話芸の奥深さに触れてみたい時など、いかがでしょうか。
以上、3年続けて「寄席の日」にちなんだ問題をお届けしました。元はといえば、3年前に「『読めますか?』の問題を何か考えてくれよ」と頼まれ、「そういえば6月の第1月曜日は『寄席の日』でしたね」とうっかり(?)応じてしまったところから始まったわけですが、よく続いたものです。漢字に興味のある方が落語に、そして落語がお好きな方が漢字に触れるきっかけになってくれていることを願いつつ、今回はこの辺で。