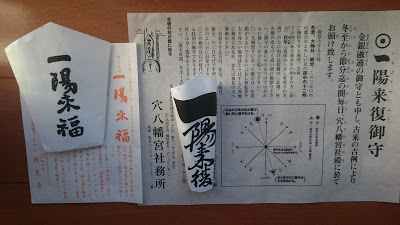読めますか? テーマは〈お盆と植物〉です。
盆花
答え
ぼんばな
(正解率 61%)お盆に盆棚に飾る花全般のこと。土地によって違うが、キキョウやオミナエシなど。盆花はキキョウの別名でもある。
(2013年08月12日)
選択肢と回答割合
禊萩
答え
みそはぎ
(正解率 71%)盆花の一種。湿地に群生し、お盆のころ紅紫色の花を咲かせる。萩と名はつくがハギとは別種。溝萩(みぞはぎ)、精霊花(しょうりょうばな)などさまざまな別名がある。禊萩は「みそぎはぎ」の縮まったという説に基づく字。漢名は千屈菜。
(2013年08月13日)
選択肢と回答割合
| くさびはぎ |
11% |
| みずはぎ |
17% |
| みそはぎ |
71% |
麻幹
答え
おがら
(正解率 45%)「苧殻」とも書く。麻の皮をはいだ後の茎のこと。お盆の迎え火、送り火にたく。また、馬に見立てたキュウリ、牛に見立てたナスに突き立て脚とする。それぞれご先祖様の乗り物とされ、盆棚の飾りに用いる。
(2013年08月14日)
選択肢と回答割合
真榊
答え
まさかき
(正解率 66%)神事に用いる木のこと。「真賢木」とも書く。「榊」は日本製の漢字。安倍晋三首相は靖国神社の4月の例大祭で真榊を奉納した。8月15日に参拝するかどうか注目されていた。
(2013年08月15日)
選択肢と回答割合
| しんさかき |
2% |
| まさかき |
66% |
| まさき |
32% |
酸漿
答え
ほおずき
(正解率 66%)「鬼灯」とも書く。大きな赤い実が特徴で、昔の子供は皮を膨らませて鳴らして遊んだ。それがほおを膨らませて指で突くのに似ていたことから「ほお突き」という名になったという説がある。ちょうちんの代わりに、ご先祖様の霊をお盆に迎えるための飾りにする。現代仮名遣いの決まりごとでは「ほうずき」としない。
(2013年08月16日)
選択肢と回答割合
◇結果とテーマの解説
(2013年08月25日)
この週は「お盆と植物」がテーマでした。

お盆といえば、校閲として要注意なのが「旧盆」の語です。「旧暦の盆」という意味なのに、8月15日前後のことを「旧盆」というケースがまま見られます。「旧盆の8月15日」は「月遅れのお盆の……」が適切。しかし今は8月に盆行事をする地方が多くなりましたので「月遅れの盆」という表記はあまり見なくなり、単に「お盆」と書くことが多くなりました。
では、それぞれの語について順にコメントします。
「盆花」はいわゆる重箱読み。「総花(そうばな)」と同じく、花を「か」と読んでしまいがちです。某局アナウンサーも「ぼんか」と誤っていたと、ツイッターで報告がありました。
代表的な盆花である「禊萩」はミゾハギともいわれます。これは溝に生えているからという語源説に基づく表記。ミソハギはみそぎに使われるからという説から。濁点のあるなしが語源にもかかわってきます。日本国語大辞典(小学館)は「『溝萩』は誤用という」としています。一方、「日本語源広辞典」(増井金典著、ミネルヴァ書房)は「みそぎ」説を「この花は禊に使うことはないので、この説は疑問」と退け、「『ミ(水)+注ぎ+萩』が語源で、墓に水をかけて供えた花、の意です」と別の説を支持しています。
「麻幹」は今回最も正解率が低くなりました。確かに難しい。ただし、きちんとした盆棚を飾る人が少なくなっていることの証左かもしれません。
「真榊」は難読とは思えないのですが、「まさかき」だと簡単すぎると思って「まさき」を選んだ人が多かったのではないでしょうか。結局、安倍晋三首相は靖国神社春の例大祭で真榊、8月15日は玉串料の奉納にとどめました。
「酸漿」は別表記「鬼灯」の方がお盆にふさわしいかもしれません。ご先祖様を迎える目印にするためですが、なぜ「鬼」の字が使われるのか、ご存じでしょうか。鬼は元々「死者のたましい」の意味だったからと思われます。「魂」の字だって「鬼」が付いていますしね。
ところで最近、根本的な疑問が寄せられました。「月遅れ盆のことをお盆というなら、7月15日に行う盆のことは何と呼んだらいいのか?」。考えたこともありませんでした。本来のお盆だから、単に「お盆」でいいのでしょうか。あるいは「7月のお盆」とするか。よく分からなかったので皆さんの声を伺いたいと思います。「私はこう呼んでいる」などの投稿をお待ちしています。