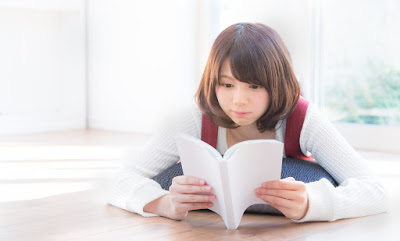読めますか? テーマは〈春の七草〉です。
目次
薺
なずな
(正解率 60%)春の七草の一つ。語源は一説に「撫(な)で菜」から。ペンペングサなどともいう。実が三味線のバチに似ていることから。「正月七日の朝、ナズナの香り立つ熱い七草粥(がゆ)を啜(すす)ると身も心も温まる思いがする」(ちくま学芸文庫「柳宗民の雑草ノオト」)
(2013年01月07日)
選択肢と回答割合
| すずな | 18% |
| すずしろ | 22% |
| なずな | 60% |
菘
すずな
(正解率 44%)「鈴菜」とも書く。春の七草の一つ。カブのこと。春の七草はほとんど文字通り草だが、これとスズシロは根菜。ただし葉も食べられる。
(2013年01月08日)
選択肢と回答割合
| すぎな | 28% |
| すずな | 44% |
| せり | 28% |
繁縷
はこべら
(正解率 62%)春の七草の一つ。「はこべ」とも読む。音読みでは「はんる」。「容易によく繁茂する上にその茎の中に一条の縷(いと)、すなわち維管束がある所からこの名が生れた」(牧野富太郎「植物記」ちくま学芸文庫)
(2013年01月09日)
選択肢と回答割合
| すずしろ | 18% |
| はこべら | 62% |
| はしばみ | 21% |
蘿蔔
すずしろ
(正解率 40%)春の七草の一つ。音読みで「らふく」。ダイコンのこと。和名は「清白」とも書く。一説にスズナの代わりということでスズシロとなったという。なおダイコンは古代には大根(おおね)といったが、中世ごろから音読みするようになったらしい。
(2013年01月10日)
選択肢と回答割合
| すずしろ | 40% |
| はこべら | 54% |
| ぶどう | 6% |
御形
おぎょう
(正解率 42%)春に黄色い小花をたくさんつける。ハハコグサ(ホウコグサ)ともいう。一般に春の七草としてはゴギョウとよくいわれるが、もとはオギョウで、植物学者の牧野富太郎によると「ゴギョウというのはよくない」(ちくま学芸文庫「植物記」)という。
(2013年01月11日)
選択肢と回答割合
| おぎょう | 42% |
| ぎょぎょう | 20% |
| ほとけのざ | 37% |
◇結果とテーマの解説
(2013年01月20日)

この週のテーマは「春の七草」でした。あとの二つは「芹」「仏の座」です。
ちなみに、鈴木棠三「日本年中行事辞典」(角川書店)によると、「七草ばやしの歌に唐土の鳥とあるのは、鬼車鳥という鳥であるとの俗説」があるとのことで「人の爪を拾って食うというので、夜爪を切らぬものなどの禁忌がある。これが転じたものが『姑獲鳥(うぶめ)』という怪鳥だともいわれる」。なんと、京極夏彦さんの小説「姑獲鳥の夏」で有名になった妖怪がこんなところに。爪切りとの関わりも俗信とはいえ面白いですね。