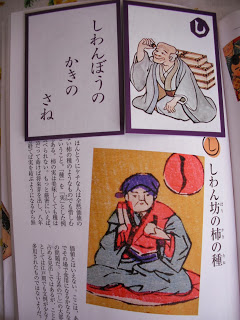読めますか? テーマは〈地道な努力〉です。
目次
虚仮の一心
こけのいっしん
(正解率 68%)「虚仮の一念」ともいう。愚か者でも一心に努力すれば成し遂げられるということ。「虚仮」は元々「真実でないこと」を表す仏教語だが、愚かなことや人の意味に変化している。
(2012年04月23日)
選択肢と回答割合
| うつけのいっしん | 17% |
| きょかのいっしん | 15% |
| こけのいっしん | 68% |
倦まず撓まず
うまずたゆまず
(正解率 73%)嫌になったり怠けたりしないこと。一つのことに努力するさまをいう。「たゆむ」の漢字は一般的に「弛む」だが、慣用句としては「倦まず撓まず」と記す辞書が多い。中には「うむ=倦む」の項で「倦まず撓まず」、「たゆむ=弛む」の項で「倦まず-まず」の例を挙げるねじれた辞書もある。
(2012年04月24日)
選択肢と回答割合
| うまずたゆまず | 73% |
| うまずたわまず | 23% |
| からまずゆがまず | 3% |
稽古
けいこ
(正解率 100%)元々は「古(いにしえ)を稽(かんがえ)る」こと。ここから「書を読んで学問すること」や「武道・芸能の修業」という意味が生まれた。「稽」は2010年の改定で加わった常用漢字。新大関・鶴竜(かくりゅう)は「これからも稽古に精進」と口上を述べた。
(2012年04月25日)
選択肢と回答割合
| けいこ | 100% |
| ほご | 0% |
| もうこ | 0% |
粒々辛苦
りゅうりゅうしんく
(正解率 92%)穀物一粒一粒は農民の労苦の結晶ということ。また、こつこつ努力すること。米作りには88の手間がかかるともいわれる(米の字を「八十八」に分解したことから)。その苦労に感謝し、ご飯は残さず食べよう。
(2012年04月26日)
選択肢と回答割合
| つぶつぶしんく | 5% |
| まいまいしんく | 3% |
| りゅうりゅうしんく | 92% |
愚公山を移す
ぐこうやまをうつす
(正解率 69%)ひたすら頑張ればどんな難事も実現するという格言。出典は中国の「列子」。愚公という90歳の老人が、邪魔な山を平らにしようと少しずつ土を移動させていた。隣人にばかにされても「子孫の代には成し遂げられる」と気にしない。その努力が神に認められ、山が移されたという。
(2012年04月27日)
選択肢と回答割合
| ぐくせんをうつす | 11% |
| ぐこうざんをうつす | 20% |
| ぐこうやまをうつす | 69% |
◇結果とテーマの解説
(2012年05月06日)