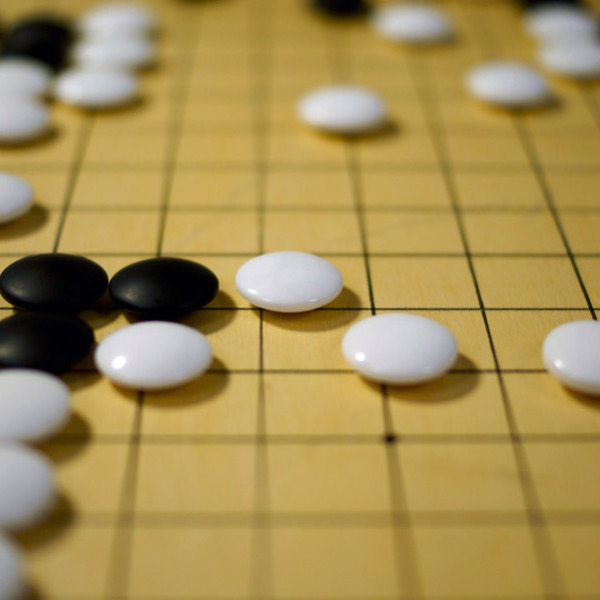読めますか? テーマは〈石川啄木〉です。
目次
啄木鳥
きつつき
(正解率 93%)「けら」とも読む。啄の字は音読み「タク」で、鳥がくちばしでつついて餌をとる意。石川啄木(本名・石川一)は18歳ごろから啄木の号を用いるようになった。啄木には「啄木鳥に」という題の詩もある。2012年は啄木没後100年。
(2012年04月09日)
選択肢と回答割合
| きつつき | 93% |
| くまげら | 5% |
| つぐみ | 2% |
猶
なお
(正解率 66%)「尚」とも書く。相変わらずという意味。石川啄木の最も有名な歌の一つ「はたらけど/はたらけど猶わが生活(くらし)楽にならざり/ぢつと手を見る」などに使われている。
(2012年04月10日)
選択肢と回答割合
| たる | 8% |
| なお | 66% |
| またたび | 26% |
為事
しごと
(正解率 34%)現在「仕事」と書くが「仕」は当て字であり、明治時代にはこの表記が少なくなかった。石川啄木は東京朝日新聞の校正をしていたころ「自分の机の上に、一つ済めば又一つという風に、後から後からと為事の集って来る時ほど、私の心臓の愉快に鼓動している時はない」と記している。生活のためというより、純粋に校正が好きだったのだろうか。
(2012年04月11日)
選択肢と回答割合
| いじ | 26% |
| しごと | 34% |
| ためごと | 40% |
閲する
けみする
(正解率 63%)「えっする」とも。よく調べること。「検閲」「校閲」の閲である。「けみ」は「検」の転じたものらしい。石川啄木は歌集「一握の砂」の序文で「この集の見本刷を予の閲したるは汝(なんじ)の火葬の夜なりき」と記した。汝とは亡児のこと。
(2012年04月12日)
選択肢と回答割合
| かんする | 10% |
| けみする | 63% |
| よみする | 26% |
夭折
ようせつ
(正解率 68%)若い時に死ぬこと。夭逝(ようせい)、早世・早逝(ともに「そうせい」)も同じ意味。石川啄木は100年前の1912年4月13日、26歳(数えで27歳)で没した。親交のあった若山牧水が臨終に居合わせた。
(2012年04月13日)
選択肢と回答割合
| そうせい | 4% |
| ようせい | 28% |
| ようせつ | 68% |
◇結果とテーマの解説
(2012年04月21日)